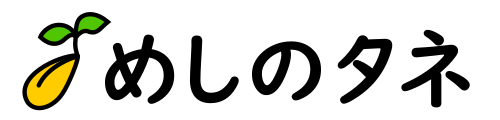安場淳さん(日本語教師)
帰国してきた中国残留孤児・2世3世の方々に対し、日本語教師として日本語を教えるだけでなく、日本で生活していくために必要な日本事情の学習支援に携わってきた安場さん。前例のない仕事で試行錯誤しながらも、帰国者の困難を少しでも減らしたいという思いで仕事に取り組んでこられた上で、「難しいからこそ、やりがいがある」とおっしゃっていました。
戦後80年が経ち、中国帰国者の存在感が日本の社会の中で薄れていく中、戦争が生み出した被害者の体験を次世代に伝えていく活動にシフトしている安場さん。昨年の日本語教師の国家資格化についてのお話も交えつつ、今後増えていく移民に対し日本語教師に求められる姿勢などを話してくださいました。どうやったら平和な日本、平和な世界を実現できるか考えつつ、読んでいただけたらと思います。
プロフィール
国立国語研究所の日本語教育長期研修を経て、中国帰国者(1990代後半からはこれに樺太帰国者が加わる)への日本語・日本事情学習支援に40年間携わる。その間、大学院修士課程での学び直しを挟む。
ここ数年は、戦争が生み出した帰国者という存在を、その家族史を通して次世代に語り継ぐ活動に注力。
中国帰国者のための日本語教師という仕事
質問 安場さんが勤めている中国帰国者支援・交流センターについて教えてください。
第二次世界大戦後、日本に帰国する機会を失い、中国や樺太(サハリン)で長く暮らした後に帰国された方々に加えて同伴して帰国された家族を支援するのが、私が勤めている中国帰国者支援・交流センター(https://www.sien-center.or.jp/)です。こうした帰国者の方々に対し、日本語学習の場を提供しつつ、日本との文化の違いによる困難を軽減していくことを目的としています。
センターは全国に7ヶ所あり、各運営団体が国からの委託を受けて事業を実施しています。2世3世などの家族も含めると、日本全国で十万人単位でいらっしゃいますね。
質問 安場さんの仕事の内容について教えてください。
私は、未就学児から90歳(!)までの帰国者への日本語及び日本事情の学習支援を担当してきました。日本語の授業と学習相談、教材開発、通信教育などですね。
日本語だけではなく日本事情も一緒に学習する必要があるのは、地域の暮らしの中でトラブルになり、お互いに嫌な思いをしないためです。帰国者は日本人ではありますが、人生のほとんどを中国などで暮らし、異なる文化で育ってきていますので、日本の文化についても学んでいただいています。
同時に、受け入れる日本社会側も、異文化と出会い、互いに共生するためのスキルを学ぶ必要がありますよね。地域社会へのそうした機会提供も仕事の一つでした。
そして今は、「語り部事業」と呼んでいますが、中国と樺太残留邦人の人生体験の伝承者育成と派遣など、日本社会への啓蒙活動の方に力を入れています。地域の方々に対して本人が体験談を話すことはどのセンターでもやってきていますが、戦後80年となる今は一世世代の高齢化が著しく、戦争の記憶が風化して忘れられる危機感から、体験を語り継ぐ人たちの育成を開始しました。
戦争が始まると、必ず難民が発生します。ウクライナやガザ地区についての報道で、戦争に対して意識が高まっている今こそ、残留邦人の体験談から、戦後何十年経っても癒えることのない傷が残ることを知ってほしいと考え、活動に力を入れています。
質問 今も帰国される方がいるのですか?
はい、昨年永住帰国されたのは1家族と、非常に少ないながらも今でもいらっしゃいます。私達のセンターには借り上げの宿舎があり、そこで日本語や日本の生活についての学習支援を受け、半年後に定住地へ引っ越していただく流れです。
センターとしての仕事は帰国者のための教育と支援ですが、支援期間が決まっているわけではありませんので、永住帰国直後の人だけでなく帰国して数十年という方もいます。そのため、今では支援の方が比重が高いです。先ほど述べたように、帰国者の高齢化により要介護の方も増えていて、彼らのQOLをいかに上げられるかがテーマになっています。
質問 安場さんも生活の支援をしているのですか?
いいえ、私は日本語教育と普及啓発が担当で、別に相談員がいて相談業務に携わっているのですが、皆で悩んで知恵をしぼっています。
いま多いのは、医療や介護の現場でのトラブル、住み替えや認知症によるトラブルですね。高齢に加えて、メンタルを患っている方が多いことも一因です。日本での生活が過酷であったり、中国でも迫害を受けたりした方が多く、歳をとることで抑えていたトラウマが噴出しやすいのです。
また2世3世も、日本ではほぼ例外なくいじめられるため、反社会的な行動に出て心を保つ場合と、メンタルをやられちゃう場合と、色々なケースがあるのです。相談員はソーシャルワーカーと同じ対人援助職として、非常に大変な仕事ではありますが、移民が増えるに伴い必要とされる仕事の一つだと思います。
質問 センターはどれぐらいの規模なのでしょうか?
私が勤め始めたころ、埼玉県の所沢に帰国者が4ヶ月間滞在して日本語や日本事情を勉強する研修施設ができたのですが、1年目の帰国者は60-70名程度だったかと思います。それが次第に増えていったため宿舎を増やし、ピーク時には年間400-500名位いましたね。
ですが、数ヶ月研修したところで日本語は身に付きませんよね。研修センターを出た後も日本語を勉強したい人たちのために、2001年に(私がいま勤めている)別のセンターが、東京の御徒町にできました。高齢化やコロナの影響もあって減りましたが、半年の受講期間で200名弱の方が参加されています。残留孤児ご本人とその配偶者世代は減少傾向で、40-60代の2世3世の方々が多く通っていますね。
質問 日本事情の学習というのは?
例えば、今の中国の若い方は割り勘もするようですが、昔の中国には割り勘の習慣がありませんでした。そのため、日本で割り勘を求められると、「日本人は冷たい」と憤慨してしまうことがありました。当初は、「それが日本の文化なのだから合わせないと」と伝えていましたが、後にそれでは帰国者側の文化を尊重していないと見直しを行い、こうした「同化」は求めないようになっていきました。その代わりに、「なぜ日本人は割り勘にするのか?なぜ中国人は必ず奢り、割り勘を嫌うのか?」というテーマで、座談会をしてみたりします。
差別されない・いじめられないことが第一ではありますけれど、日本式を押しつけてはなりません。ではどうやって伝えるべきことを伝えるのか、悩みつつ方法を模索していきました。
なぜ帰国者の支援を終わらせることができないのか?
質問 2世3世の方も日本語を学びに来ているのですか?
はい。しかしながら、その多くが「呼び寄せ家族」です。
国は、残留孤児本人と配偶者までを支援対象としていて、後から呼び寄せた2世3世は対象ではないというスタンスです。ルールが複雑なのですが、高齢帰国者の面倒を見るために、1世の永住帰国時に同伴で来日した2世3世は支援対象です。が、一人っ子政策が始まる前の中国は子沢山でしたので、一緒に暮らしたいと後から日本に呼び寄せた2世3世がたくさんいます。これらの2世3世は、国の支援の対象外なのです。そのため、国がその方たちのためだけに何かをすることはないが、余っている席があればセンターに来てもいいよ、という形で受け入れているのです。
――時間が経つにつれて支援の対象者は減ると思っていたのですが……。
国もそう思っているのですが、そう簡単ではなかったのです。
例えば1世が80代で、呼び寄せた2世が50代だとします。その歳になってから日本語を勉強するというのは、無理があります。40年前に40代で帰国した残留孤児の方々も、同じ苦労をしました。日本にずっと住んできた日本人は「言葉なんて教えられればできるようになるはず」と簡単に言うのですが、帰国者の中には、中国で学校に行ったこともない、鉛筆を持ったこともない人がいるのです。「30年も勉強して、何で日本語ができないの?」と言われても、頑張ってもできない人もいるのです。それでも、自分は日本人だから勉強したいと、学びに来ています。
そして「3世ならもう大丈夫だろう」と言う人もいますし、そういう家庭ももちろんあります。が、2世の方が3世である子どもを日本に連れてきたとしても、日本で3世を産んだとしても、仕事が忙しいために中国の親族に預けるということが多いのです。そうすると日本語ができませんよね。それで3世が、学校の卒業のタイミングなどで日本に戻ってきたとしても、日本語にハンデを持っているのです。4世でも同じように困っている人はいるのですが、制度上は3世までしか対象にできず、歯がゆいですね。
――私も3世ならもう大丈夫だろうと思っていました。
帰国者3世に限らず、他の外国にルーツがある子も同じなのですが、学校では言葉では困っていないように見えても、両親とも日本語がよく分からないとなると、宿題を見てもらえなかったり、学校からの伝達事項を取りこぼしていたりで、なかなか勉強についていけない子もいるのです。本人の責任のように思われてしまいがちですが、実際は環境のせいです。
以前は小中学校で補習という形でやってはいたのですが、最近では子どものための日本語教育は正式な課程となって、高校でも単位として認められるようになったので、子どもの日本語教育に携わりたいという人は増えていますね。
日本語教師になるまで
質問 元々、日本語教師を目指していたのでしょうか?
大学では英文学を専攻し、消去法で選んだ結果、英語教育のゼミに入っていました。今となっては、英語を話そうとしても中国語がでてきてしまいますが(笑)。
それで、自転車旅行で当時住んでいた京都から九州に行った際に、福岡でボートピープル(ベトナム戦争後にボートで国外避難したインドシナ難民)の方が開いたベトナム料理屋さんがあるということで、当時は珍しかったので行ってみたのです。そこに自分と同じぐらいの歳のお子さん達がいたのですが、互いの言葉が分からず意思疎通ができなくて。そのときに、日本語教師というのは需要があるかも?と思ったのがきっかけでした。
それで京都に戻ってから探していたら、国立国語研究所で1年間の日本語教育研修というのがあると教えてもらえて、経験もなかったので受かるかわかりませんでしたが、受験してみようと考えました。当時は大学の教員養成課程に、日本語教師というのは無かったですしね。
研修が終われば、皆それぞれを雇ってくれるところに行くのですが、ちょうど今勤めているセンターの前身が翌年に開設されることが決まり、そこで多くの人手がいる……と。馬車馬のように働いてくれる人が欲しいと言われましたね。5年ぐらいで終わるという話だったので、経験を積ませてもらって他のところに行くつもりで就職したのですが、結果として40年いてしまいました。
――馬車馬ですか!
当時は残業代もないし、本当に馬車馬のように働きましたね。
帰国者のための日本語教材の試作品が開発されたところでしたが、帰国者には合わなくて結局使わなくなり、翌日の授業の教材も本当に何もなかったので、自転車操業でした。明日の授業で何をしようか考えながら寝てしまって、電車を乗り過ごしたり……と、20代だったからできたことです。先ほどお話しした通り、私の仕事は当時の普通の日本語教師とは違う難しさと、毎回予想通りにいかない面白さがあるので、長く続けられたのかもしれません。
質問 途中で大学院に行かれたそうですが、何を学び直したのでしょうか?
発達心理学なのですが、それを学びたかったからではなくて……。実は、当時は日本在住で外国の文化を持つ人の教育やサポートを専門にしている学科がなくて、異文化間心理学が専門の先生が発達心理学の学科にいらしたので、そこに行こうと考えたんですね。この時は、専門外だった分野の受験勉強でしたので、人生で一番ぐらい必死でやりました。
しかしながら、当時の異文化間心理学の研究領域は、日本人が海外に行くとか、帰国子女が日本にどう適応するかという意味での異文化だったので、海外から日本にやって来た人に対するものはほとんどなかったのですが。
それで、なぜ学び直そうと考えたかというと、就職して必死に働いて4-5年ほど経ったときだったのですが、常に目先のことに追われていることに気づきました。大切な人たちにより良い教育を提供するためには、もっと勉強しないといけないのではないかと思ったんですね。それで一度リセットしようと思って大学院に行くことにしたのですが、人手が足りなかったのもありますが、私もお金がなかったので、大学院の2年間も同じセンターに非常勤で勤めました。そういうわけで、結局はあまりリセットできませんでしたね(笑)。それでも、勉強の時間は確保できましたし、どのみち自分たちの前に道はなかったから、自分で拓いていけばいいんだと思えて、充実した時を過ごすことができました。
日本語教師を目指す方たちへ
質問 稼げますか?
帰国者をはじめとする生活者のための日本語教師の仕事は、福祉としての位置づけが強いので、「稼げるか?」と聞かれると答えにくいですね。しかし、昨年から日本語教師が文科省の国家資格となったことで、状況が変わっていくかもしれません。
昔は日本語教師といえば、留学生が通うような日本語学校やビジネスパーソンを対象としていました。それが、国家資格ではこの留学のための課程に加え、生活のための課程と就労のための課程という3つの部門に分かれました。帰国者の必要とする日本語はその生活のための日本語で、「地域日本語」とも呼ばれています。留学生でもビジネスパーソンでもない、日本に定住していくための日本語のことですね。
今、技能実習生として日本に住んでいる人も大変多いのですが、この技能実習も、外国人労働者の権利の保護強化とキャリア形成を目指す育成就労制度に変わろうとしています。
――地域日本語という用語は初めて聞きました。
日本では、中国帰国者と並行してインドシナ難民を受け入れた時代があり、1990年代には日系ブラジル人の時代を経て、今ではありとあらゆる国の方たちが日本に来ています。これらの方々の地域社会に参入するための日本語というニュアンスでの「地域」と考えていただければよいかと思います。そして、どの国の人の移住にも、その国と日本との関係の歴史が絡んできます。
日本語教師の国家資格化は画期的なことで、なぜかというと「移民を受け入れる」という前提に立っているからです。これから移民が増えていくとすれば、留学生以外の日本語教師の需要が高まり、稼げるようになるかもしれません。国家資格になることで日本語教師の地位の保障は進むだろうとは思いますが、これからどのように社会がどう変わるか次第で、まだまだこれからだと思います。
――稼げるか稼げないかは、これからの移民政策に注視する必要があるということですね。
はい、ただ日本のサブカルチャーに惹かれて来る人はいても、働きに来たいという人は減るんじゃないかと心配しています。円安に加え、日本が欲しがっている介護や建設、農業などの分野は、これだけ人材不足で困っているのに低賃金ですから。まずはその部分を本気で改善しないと、日本に来たいとは思わないですよね。
――日本語教師の地位は向上するだろうとのことでしたが。
のはずですが、今は過渡期と言えます。
質問 そのような中、日本語教師に必要なスキルは何だと思いますか?
生活のための日本語と日本事情を学ぶ人たちへの支援においては、資格だけでは役に立たず、むしろ非識字者を含む幅広いバックグラウンドを持つ方々のニーズに応えられるかどうかだと思います。そのためには、目の前にいる人の個人としての背景に加え、国としての背景についても知る努力を怠らず、彼らのニーズを見極める目を養い、その実現を手助けできる技術を自ら育む力が不可欠です。
あとは、日本語学習支援には学習者の母語が分かることは必須ではなく、逆に分からない方が、本物のコミュニケーションの場を生み出すことができるとも言われています。これを私のケースに当てはめると、私が中国語を理解する必要はないという意味ですが、言語としての違いからくる学習上の弱点を知ることや、その人のその時々の気持ちを知るために、彼らの母語、もしくは双方でコミュニケーションの取れる言語が分かることはプラスになりますね。
質問 仕事をしていて嬉しいことは何ですか?
語学教師は誰でも同じだと思いますが、「通じた!」という喜びを共有できたときですね。それから、関わってきた人が、日本で人生を切り開いていってくれていると感じられたときです。
伝承事業においては、語り部の話を聞いた方が、帰国者の個人史から彼らの家族、地域、そして国と、広く歴史に対する目を持ってくれたと感じられたときは、本当に嬉しいですね。
質問 逆に苦労されていることは何ですか?
学習支援に関しては、日々の暮らしに追われている帰国者たちに、達成感を持ってもらうことです。中高年になると、分かった!通じた!と喜べたことも、翌週には忘れてしまっているものです。そこでがっかりしすぎず、自らの目標を設定し直せるかどうか、に苦労したりしています。
伝承事業においては、若い人たちに自分の生まれる前の時代へ思いを馳せてもらうことに、難しさを感じます。いずれも難しいからこそ、やりがいがあるのですが。
安場さんから、子ども達へのメッセージ
「身近にいる言葉や文化が異なる人と、どうやって暮らしあっていくか?」という問題に対し、助ける/助けられるという関係だけではない答えを、協力して見つけ出していって欲しいですね。そういう仕事は今後増えていくはずですし、逆に新しい世代の方たちには、次々と生み出していって欲しいと願っています。
安場さん、ありがとうございました!